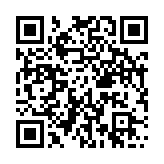|
最新更新日:2024/06/05 |
|
本日: 昨日:162 総数:671842 |
5年生 おやつ作りをしました(2月27日)





蒸しパンを作るにあたって、水の量が多かったり少なかったり、さつまいももちは焼きすぎてちょっと焦げてしまったり、ちょっとした失敗もありつつ、友だち同士でわいわい言いながら楽しそうに作っていました。 完成品をいただく際には、自分で作ったランチョンマットを使って食べました。 お茶を入れるところから始まった家庭科ですが、今ではいろいろなことができるようになっています。ぜひお家でも、これまでに学んだ成果を発揮してほしいと思います。 最後の学習参観の様子です 5年生(2月24日)





子どもたち一人ひとりが考えた自分の「もち味」を、担任の先生が名前を伏せて発表していきました。その中で、それは誰のことなのかを考える活動を通して、より友だちのことを深く知るというとりくみでした。 もうすぐ最高学年となる5年生ですが、今の自分や友だちをあらためて見つめ直し、来年度に向けて気持ちを新たにする良い機会となったようです。 5年生 太鼓作りをしました!その3(2月14日)

本日参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました! 5年生 太鼓作りをしました!その2(2月14日)





徐々に完成が近づいてくるにつれて、「かっこいいやん!」「お母さんが欲しいわ!」という声も聞こえてきました。そしておよそ1時間〜1時間半をかけて世界に一つだけのオリジナル太鼓が完成しました。 5年生 太鼓作りをしました!その1(2月14日)





昨日の準備に引き続き、今日も地域にお住まいの北出さんが、作り方の主な指導をしてくださいました。また、太鼓作りをはじめ、いろいろな行事でお手伝いくださる地域の方や、北出さんのお知り合いのかたなどもスタッフとして参加してくださいました。 精肉店とともに太鼓屋も営んでおられる北出さんの技はさすがで、とても手際よく、きれいな太鼓を作っていかれます。北出さんが手本を見せるとなると写真のような人だかりができていました。 5年生 太鼓作りの準備をしました(2月13日)





牛の皮には本来たくさんの毛が生えていますが、北出さんが「ぬかなめし」という方法でその毛をきれいに取ってくれています。そして太鼓のサイズに切り分けてくれた2枚の皮に、子どもたちがポンチという道具と金づちを使って穴を空けていきました。牛の皮は乾かすととても堅く頑丈になり、水に浸すと柔らかくなるため、昔から太鼓をはじめいろいろな道具に利用されてきました。昨日から水に浸していたということもあり、皮はとても柔らかくなっていたものの、穴を空けるとそう簡単にはいかず、子どもたちは何度も金づちで叩き、時には指を叩いてしまうこともありながら穴を空けきりました。 明日は太鼓作りの本番です。今日準備をした皮を、実際に胴となる筒に紐を使って縛り付けます。とても力の要る作業なので、お家の方や地域のボランティアスタッフ、教職員と一緒に作り上げていきます。牛の命を分けていただいた皮は二つとして同じものはなく、また自分で作るオリジナルの太鼓は世界でたった一つのものです。ぜひ明日は素敵な太鼓を作ってもらいたいと思います。 5年生 北出さんからの聞きとり(2月3日)

子どもたちにとっても、牛乳を飲んだりお肉を食べたりする機会が多いので、牛は身近な動物です。まずはそんな牛の種類や特徴についてのお話をしてくださいました。単純に牛と言っても、種類や人間との関わりはとても多様で奥が深いということを学びました。 次に北出さんのお仕事についてのお話でした。北出さんは子どものころから50年近く、牛を育ててお肉にする仕事をされています。「人間が生きていくために命をいただいている」と気持ちを込めて語りかけてくださり、子どもたちも命をいただくことの尊さについて考えることができました。最近は、精肉の仕事以外にも、北出さんは太鼓を作る仕事をされています。自分の町のだんじりの太鼓が、北出さんに皮を張ってもらったと知って、子どもたちも驚いていました。このように、人間の都合で牛の命をいただいているので、北出さんは決して牛を「殺す」とは言わず、「わる」という言葉を使われます。また、北出精肉店の敷地内にある獣魂碑についてもお話してくださいました。 子どもたちの命をつくるお肉や、暮らしを支える道具、そして料理ができるまでに関わってくださる人への感謝の気持ちを忘れてはいけないとお話してくださいました。最後に、みんなそれぞれたくさんの命をつないで生きている大切な命なので、友だちを大切にしてほしいということもお話されました。 北出さんご一家のお仕事を映画化した「ある精肉店のはなし」も全国で放映され続けていて、北出さんご自身も全国各地を飛び回っておられます。そんな忙しい中、東小学校の子どもたちのためにおこしいただき、本当にありがとうございました。 |
貝塚市立東小学校
〒597-0021 住所:大阪府貝塚市小瀬1丁目25-5 TEL:072-422-0262 FAX:072-431-2987 |
|||||||||